ロードバイクは、スピード感と長距離走行の快適さを兼ね備え、多くのサイクリストに愛されてきました。
しかし近年、「ロードバイクは売れていない」「オワコン(終わったコンテンツ)ではないか」といった声がSNSや自転車関連フォーラムでたびたび話題となっています。
この記事では、最新の市場データと専門家の見解をもとに、ロードバイクの現状と将来性について詳しく解説します。
特に、業界最大手シマノの動向を中心に、初心者の方にもわかりやすくお伝えします。

オワコン説の根拠と実態

日本国内でオワコンと言われる5つの具体的理由
理由1|新規ユーザーの減少
コロナ禍のピーク時に一気に自転車人口が増えた反動で、2023年以降は新規参入が落ち着いています。
理由2|価格高騰
2020年以降の円安と部品供給不足により、同じグレードのロードバイクでも価格が平均20〜30%上昇しています。人気モデルの価格は数年前と比較して大幅に値上がりしています。
理由3|初心者の敷居の高さ
ロードバイク特有の乗車姿勢や細いタイヤ、複雑なギア操作などが初心者にとっての障壁となっています。「乗りこなす自信がない」という理由でロードバイクの購入を見送るケースが多いようです。
理由4|競合製品の台頭
クロスバイク、グラベルバイク、eバイクなど、より扱いやすく多用途な自転車カテゴリーの人気が上昇しています。特に電動アシスト自転車は販売台数が増加傾向にあり、ロードバイクからの乗り換え事例も増えています。
理由5|個人の自転車屋さんへの影響
多くの個人経営の自転車店は、創業者が高齢化しているにも関わらず後継者が見つからないという問題を抱えています。自転車店はもともと低利益率であり、特にロードバイクのような高価格帯商品は販売サイクルが長いため、安定した収益を確保するのが難しいです。このような厳しい経営環境の中で、若い世代が自転車店を継ぐことに魅力を感じない状況が続いています。
シマノに焦点を当てる理由

シマノは、世界最大の自転車部品メーカーであり、特にロードバイクのギアやブレーキといったコンポーネントでトップシェアを誇ります。シマノの業績や製品動向は、ロードバイク市場全体の健康状態を示す重要な指標です。初心者の方でも、シマノの動向を理解することは、ロードバイク市場の全体像を掴むために非常に有益です。そのため、本記事ではシマノの最新決算を活用し、市場分析を行います。
ロードバイクの市場動向【2025年最新】

シマノの最新決算から見る市場の実態
シマノの2025年第1四半期決算によれば、売上高は1,135.39億円(前年同期比12.9%増)、営業利益は161.42億円(同20.3%増)と増収増益を達成しています。しかし、為替差損の影響で経常利益と純利益は減益となっており、親会社株主に帰属する四半期純利益は97.86億円(同58.7%減)でした。この為替の影響は、ドル安によるアジア通貨高が主な要因です。ー参照:日本経済新聞ー
日本国内市場の課題
日本国内では、ロードバイクの売れ行きが低迷しています。大手自転車店からの報告によれば、ロードバイクの販売は減少傾向にあり、新規参入者も少なくなっています。その一方で、価格帯の安いクロスバイクや、価格が高くても電動自転車が売れています。これは、消費者がより実用的で日常生活に合った自転車を選ぶ傾向が強まっていることを示しています。
消費者ニーズの変化
消費者は、通勤や買い物に使える実用性を重視する傾向が強まっています。クロスバイクはその手軽さと価格の手頃さから、通勤や日常の移動手段として人気を集めています。また、電動自転車は坂道が多い地域や長距離の移動が必要な場面での利便性から支持されています。これに対し、ロードバイクは趣味性が高く、日常の利便性よりもスポーツやレジャー向けの特化した用途が求められるため、購入層が限られています。
全体像|コロナ特需の終焉と市場の二極化

2020年からのコロナ禍で、自転車市場全体は一時的に活況を呈しました。
しかし、2022年以降は需要が一巡し、特に高価格帯のロードバイクの販売に頭打ち感が出てきています。
経済産業省の統計や自転車業界団体のデータを参照すると、2023年から2024年にかけてロードバイクの国内出荷台数はやや減少傾向にあります。
ただし、この現象は一概に「売れていない」とは言い切れません。
むしろ、コロナ特需の反動による市場の正常化と捉えるべきでしょう。
また、注目すべきは市場の二極化です。
明暗が分かれるロードバイク市場|高級モデル vs エントリーモデル

大手自転車店からの報告によれば、ロードバイクの販売は減少傾向にあり、特に新規参入者が少なくなっています。
「2020年はロードバイクが飛ぶように売れましたが、現在は…クロスバイクや電動アシスト自転車の販売が好調です」(関東圏:大手自転車店)
このように、日本国内では「ロードバイクが売れていない」という現場の声が多く聞かれます。
その代わりに、価格帯の安いクロスバイクや、価格が高くても実用性の高い電動自転車が売れているという状況だそうです。
1.高級モデル市場

カーボンフレームや電動変速システム(Di2など)を搭載した30万円以上のハイエンドモデルは、コアなファン層に支えられて比較的堅調に推移しています。
2.エントリーモデル市場

20万円前後のアルミフレームを中心とした入門モデルは、クロスバイクや電動アシスト自転車にシェアを奪われ、苦戦しています。
特に顕著なのがミドルレンジ(10〜20万円)のロードバイク販売の落ち込みです。
この価格帯は従来、趣味として始めるユーザーの主要な入り口でしたが、現在はクロスバイク(5〜10万円)に流れるか、より実用性を求めて電動アシスト自転車(25〜45万円)を選択するケースが増えています。
新規参入の壁と既存ユーザーの高齢化
日本市場においては、ロードバイクへの新規参入のハードルが高いという課題も存在します。

- 価格の高さ:ロードバイクを始めるには、初期投資だけでなく、ランニングコストとしてのメンテナンス費用も考慮する必要があり、これが手軽に始めることを難しくしています。
- ウェアの問題:専用のサイクリングウェアは、機能性に優れている反面、価格が高く、ファッションの自由度が制限されていると感じる人が少なくありません。
- 保管場所の確保:特に都心部では、ロードバイクを安全に保管するためのスペースを見つけることが課題となっています。
- 安全性の不安:交通量の多い道路での走行は、特に初心者にとっては安全面での不安を感じやすい状況です。

さらに、既存ユーザーの高齢化も懸念材料です。
若年層の新規参入が減少する一方で、既存のロードバイク愛好家の平均年齢は上昇傾向にあります。
海外市場との比較|明暗を分ける市場環境

日本市場が低迷する一方、海外市場、特に欧州と北米では状況が異なります。
欧州市場:環境政策の強化や自転車インフラの整備を背景に、ロードバイク市場は堅調に推移しています。
特に電動アシスト付きロードバイク(eロードバイク)の成長が著しく、高機能モデルへの需要シフトが進んでいます。
参照:https://www.conebi.eu
北米市場:カジュアルユーザー向けの入門モデルと、本格的なサイクリスト向けの高級モデルへの二極化が進んでいます。特にグラベルバイクレースの人気上昇に伴い、関連製品の需要が増加しています。
参照:https://www.peopleforbikes.org
アジア市場:アジア市場に目を向けると、そのコントラストは鮮明です。中国では中間所得層の拡大と健康志向の高まりを背景に、ロードバイク市場が目覚ましい成長を遂げています。中国自転車協会の発表によれば、2023年の中国国内のロードバイク販売台数は前年比16.5%増の約68万台と大幅に増加しています。最新の上海サイクルショーでは、国内外のブランドが最新モデルや技術を競い合い、活気に満ちた商談が繰り広げられました。
台湾で開催される台湾サイクルショーも、世界中からバイヤーが集まり、アジア市場のトレンドセッターとしての地位を確立しています。
しかし、目を日本国内に向けると、状況は一変します。かつては賑わいを見せた日本最大級の自転車イベント、サイクルモード東京も、近年は会場規模の縮小や出展者の減少が否めません。かつては熱気に満ち溢れた会場も、今は寂しさが漂うという声も聞かれます。
参照:https://www.statista.com
ある店舗の店長からのご意見

結論|ロードバイク市場は「オワコン」ではない—多様化と専門化の時代へ

ロードバイク市場は、かつての爆発的な成長期を終え、成熟期を迎えています。
日本国内においては、価格高騰、維持コストの高さ、専門店の減少など、様々な要因が重なり、販売台数は減少傾向にあります。
しかし、「オワコン」という言葉で片付けるのは早計です。
市場は確かに変化しており、ロードバイク一辺倒の時代は終わりを告げました。
クロスバイク、グラベルバイク、eバイクなど、多様なカテゴリー台頭し、消費者は自身のライフスタイルや目的に合わせて最適な一台を選ぶようになっています。
しかし、ロードバイクが持つ独自の魅力—軽快な走行性能、長距離走行の快適性、そして何よりもスポーツバイクとしての純粋な魅力—は、決して失われることはありません。
実際、高級モデル市場は比較的安定しており、熱心なファン層に支えられています。

今後は、ロードバイク市場は「大衆化の時代から本格派の時代へ」と移行すると考えられます。
ロードバイクは、より専門的な知識や技術を求めるコアなユーザーに支持され、グラベルバイクやeバイクは、より幅広い層に手軽なサイクリング体験を提供する—そんな未来が待っています。
重要なのは、「ロードバイクVSその他」という二項対立ではなく、用途に応じた適材適所の自転車選びです。
サイクルツーリズムとの連携や、高齢者向けサービスの拡充など、新たな可能性も広がっています。
日本のロードバイク市場は、今まさに転換期を迎えています。
過去の成功体験にとらわれず、変化を恐れず、新たな価値を創造していくことこそが、市場の再活性化につながるでしょう。
「ロードバイクは終わった」そう囁く声に耳を傾けるのではなく、ロードバイクが持つ本質的な価値を再認識し、新たな可能性を追求していくことこそが、これからの時代に求められているのです。
記事作成者|今田イマオ

【キャリア概要】
自転車メディアで編集長を務めた後、SEOを考慮したコンテンツ制作を得意とするディレクターとして、2019年4月に株式会社自転車創業に入社。現在、フリーランスとしてライティングから動画編集、出演まで、総合的なメディアコンテンツのディレクション実績1000本以上の制作に携わるマルチプレイヤーとして活躍中。
【専門分野】
- SEO最適化コンテンツ制作
- ライティングおよび動画編集
- マルチプラットフォームでのコンテンツ展開
- 自転車業界でのインフルエンサー活動

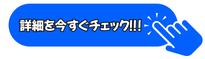
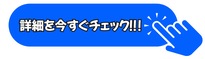
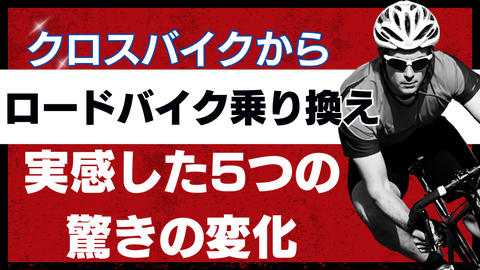



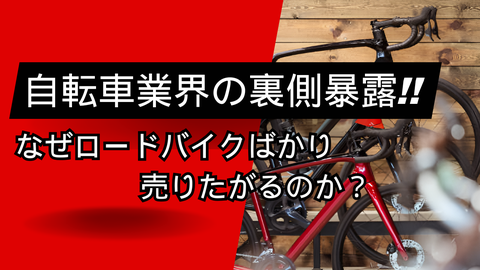

コメントをお書きください